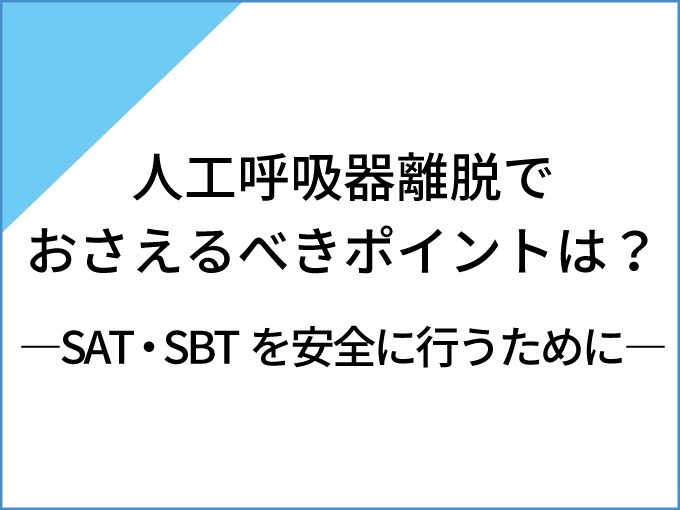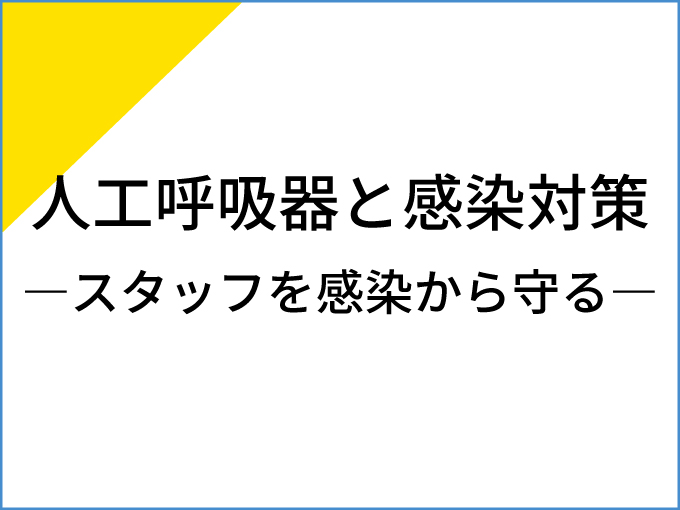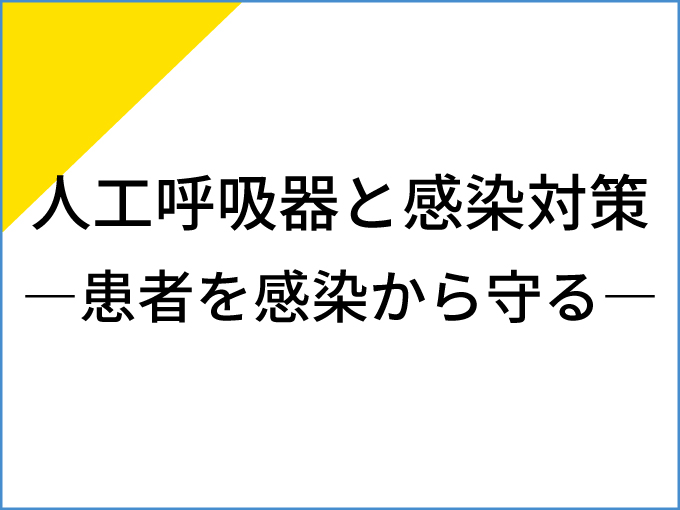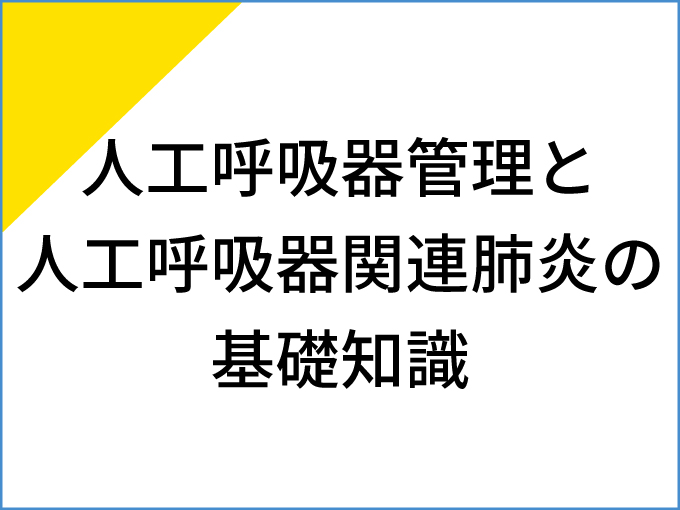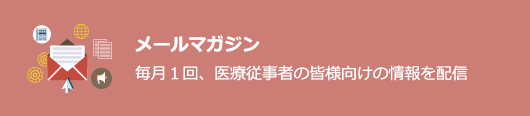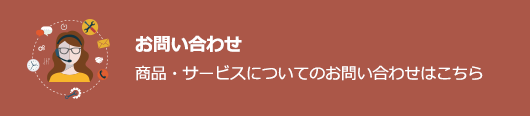人工呼吸管理時の感染対策チェックリスト ―実践編―
- 掲載:2024年05月
- 文責:メディカ出版


これが重要!指導のときに必ず伝えたいポイント
ポイント1
ウィズコロナにおける人工呼吸管理時の標準予防策について、患者と医療従事者双方を守る視点で十分議論しておく。
「医療機関における新型コロナウイルス感染症ヘの対応ガイド」のなかで、臨床の現場でエアロゾル発生量が増える可能性がある手技においては、慎重かつ適切な対応をする必要があると記載されているが3)、人工呼吸管理では複数のこのような手技が想定される。
コロナ禍ではCOVID-19確定患者ではなくても、誰もが感染している可能性を考え、標準予防策として曝露部位を予測しPPEを使用する。また状況によりN95レスピレータ着用を考慮する。
また、エアロゾル産生手技ではないが、人工呼吸器を装着した患者の処置を行う場合には、標準予防策に応じたPPEを選択する。曝露部位の予測に応じサージカルマスク、アイシールド、手袋、ガウンを確実に着用する。
人工呼吸管理中の患者は眼・鼻・ロの粘膜があらわになっており、一般の患者以上に病原体に感染しやすい状態である。職員が万が一にも感染していた場合、適切なPPE着用と確実な手指衛生を行わなければ患者へ感染させる可能性があることをつねに意識して行動する。
ポイント2
VAP予防バンドルおよびベッドサイドケアの見直し、実践、評価、改善の継続が必要である。
VAP予防については、国内では2010年に日本集中治療医学会のICU機能評価委員会よりVAPバンドル6)が公開されており、2014年に米国医療疫学学会(SHEA)および米国感染症学会(IDSA)により、「急性期病院におけるVAPを予防するための戦略」が発表され、さらに2022年5月に内容が更新された4)。
また本戦略は成人のみでなく、新生児や小児についても触れている。2018年にはVAPバンドルの研究として、スペインのICU「Pneumonia Zero」プログラムのマルチモーダルアプローチが公開されている7)。
このように複数のバンドルや推奨事項が存在するなかで比較すると、推奨内容が一致するものもあれば、そうでないものもあり、エビデンスの読解と考察が必要となっている。たとえば、VAP予防のためのクロルヘキシジンによる口腔ケアについて、「Pneumonia Zero」プログラムではクロルヘキシジンロ腔内消毒をバンドルのなかでも必須な対策の一つとしている(表17)の“7つの基本的な必須対策”の④)。
一方、2022年に更新された「急性期病院におけるVAP、人工呼吸器関連事象(VAE)、および非人工呼吸器院内肺炎(NV-HAP)を予防するための戦略」の推奨事項ではクロルヘキシジンの口腔ケアは“一般的に推奨されない”としており、クロルヘキシジンを含まない毎日のブラッシングで口腔ケアを提供することを必須プラクティスとしている表24)。国内では、クロルヘキシジンによる複数のアナフィラキシー発生の報告もあり8)、医療用医薬品として口腔粘膜に使用することは禁忌であるが、一般用医薬品で低濃度の製品であっても、過敏症既往歴を確認するなど、使用にあたっては慎重に検討をする。
口腔ケアの実践方法として、日本クリティカルケア看護学会口腔ケア委員会は、「気管挿管患者の口腔ケア実践ガイド」9)を公開するなど、口腔内由来感染防止のためのケア方法は各方面で注目されている。
実際にどのように行うかは施設で十分に検討したうえで手順を作成し、統一した手技で実践し評価していく。
表1:「Pneumonia Zero」プログラムのVAP予防の個々のコンポーネントバンドル
7つの基本的な必須対策
- ①適切な気道管理の教育と訓練*
- ②気道管理前の擦式アルコール製剤による厳格な手指衛生
- ③カフ圧の制御と維持
- ④クロルヘキシジンによる口腔内消毒
- ⑤セミリカンベントポジショニング
(可能であれば0度の仰臥位を回避) - ⑥人工呼吸器の使用を安全に回避または短縮する手順とプロトコルの促進
- ⑦人工呼吸回路、加湿器、および気管内チューブの選択的交換の回避
強く推奨される3つの対策
- ①消化管の選択的除染または選択的口腔咽頭除染
- ②継続的なカフ上部吸引
- ③以前に意識が低下した患者の挿管中の抗菌薬の短期コース(2~3回の投与)
*VAP予防と患者の安全性に関する2つの教育モジュールと、それに対応した試験をオンラインで自由に閲覧でき、試験に合格したICUスタッフを継続的にモニタする。各ユニットのコーディネータは、このレジストリにアクセスし、地域のコーディネータに報告する。慢性閉塞性肺疾患の急性増悪時の非侵襲的機械換気、離脱または鎮静のための低用量注入またはその毎日の中断を促進するためのプロトコルが利用可能である。
(文献7より作成)
表2:成人患者におけるVAPやVAEを予防するための推奨事項の概要(2022年更新)
| カテゴリー | 根拠 | 介入 | エビデンス の質 |
|---|---|---|---|
| 必須のプラクティス | 人工呼吸器の平均期間、入院期間、死亡率および/または費用が減少する良好な証拠で利点がリスクを上回ると考えられる。 | 挿管を避ける、また再挿管を防止する。 ・鼻腔高流量酸素療法または非侵襲的陽圧換気(NPPV)は、安全で実行可能な場合、いつでも適宜使用する。 |
高 |
鎮静を最小限に抑える。 ・ベンゾジアゼピンを避けてほかの薬剤を選択する。 ・鎮静を最小限に抑えるためのプロトコルを利用する。 ・人工呼吸器離脱プロトコルを実施する。 |
中 | ||
| フィジカルコンディショニングを維持・向上させる。 | 中 | ||
| 30~45度のギャッチアップをする。 | 低 | ||
| クロルヘキシジンを使わすに歯ブラシで口腔ケアを提供する。 | 中 | ||
| 経腸栄養と静脈栄養を早期に提供する。 | 高 | ||
| 人工呼吸器回路の交換は、目に見える汚れや故障がある場合(またはメーカーの指示に従っている場合)にのみ行う。 | 高 | ||
| 追加アプローチ | 一部の集団ではアウトカムが改善することを示す十分な証拠があるが、ほかの集団では何らかのリスクをもたらす可能性がある。 | 抗生物質への耐性菌の少ない国やICUでは、選択的口腔内除染や消化器内除染を行う。 | 高 |
| VAP発生率を低下させる可能性があるが、人工呼吸器使用期間、入院期間、または死亡率への影響を判断するにはデータが不十分である。 | 48~72時間以上の人工呼吸が必要と予測される患者には、カフ上部吸引機能付き気管内チューブを使用する。 | 中 | |
| 早期の気管切開を考慮する。 | 中 | ||
| 胃不耐性または誤嚥のリスクが高い患者には胃からの栄養よりも幽門後栄養を考慮する。 | 中 | ||
| 一般的に 推奨されない |
VAP発生率の低下との関連は一貫しておらず、人工呼吸器使用期間、入院期間、または死亡率に影響または悪影響を及ぼさない。 | クロルヘキシジンによる口腔ケアを実施する。 | 中 |
| プロバイオティクスを考慮する。 | 中 | ||
| 極薄ポリウレタン製のカフ付き気管内チューブを用いる。 | 中 | ||
| テーパー型カフ付き気管内チューブを用いる。 | 中 | ||
| 気管内チューブカフ圧自動制御を用いる。 | 中 | ||
| 頻繁なカフ圧モニタリングを行う。 | 中 | ||
| 銀コーティングされた気管内チューブを用いる。 | 中 | ||
| 自動体位変換ベッドを用いる。 | 中 | ||
| 腹臥位とする。 | 中 | ||
| クロルヘキシジン入浴を行う。 | 中 | ||
| VAP発生率、人工呼吸器の平均期間、入院期間、または死亡率に影響はない。 | ストレス潰瘍予防を行う。 | 中 | |
| 残存胃容積のモニタリングを行う。 | 中 | ||
| 早期静脈栄養を行う。 | 中 | ||
| 非推奨 | VAP発生率やほかの患者のアウトカムヘの影響はなく、コストに対する推奨の影響は不明である。 | 閉鎖式気管内チューブ吸引システムを用いる。 | 中 |
*「カテゴリー」は客観的な結果の改善に関する肺炎予防戦略を優先しており、「介入」の実現可能性やコストなどとのバランスを考慮している。たとえば「介入」の「30~45度ヘッドアップをする」のエビデンスは「低」で、結果への影響は不確実ではあるが、介入のシンプルさや最小限のリスクでコストがかからないことから、「必須のプラクティス」に分類される。
表24)から自施設のVAPバンドルを検討する際、まず「必須のプラクティス」から自施設で実践可能なものを選択したうえで改善がなければ「追加アプローチ」を参考にするとよいと考える。表2の「一般的に推奨されない」「非推奨」のものでも、VAPやVAE以外を含めた患者ごとの特徴や施設背景をもとに利益がある場合は採用を検討する。
(文献4より作成)
ポイント3
特にウィズコロナでは多職種間でベッドサイドの感染対策を踏まえた情報を共有し、チームで取り組んでいくことが大切である。
コロナ禍において患者の隔離対応が増えるなか、どの程度ベッドサイドカンファレンスが行われているだろうか。
ベッドサイドで患者の状態を見ながらのカンファレンスができない場合には、どの職種も同じ視点で観察やケアが行えるよう、情報の共有をしておくことは非常に大切である。
急性期病院の重症患者の治療においては、人工呼吸器のみでなく、体外式膜型人工肺(ECMO)や補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)などが付与される場合もあり、「どのように状態を判断し、離床やケアを行うか」「VAPバンドルを実践するか」など、現場で悩むことも多いはずである。感染対策においても、隔離病室の中での職員の曝露予防や患者の病院感染防止は、担当者の技量によるところが大きくなる。
カンファレンスでは治療や病態生理の内容に加え、ベッドサイドのケア場面においても感染対策を考慮した議論がされるようなアプローチが望まれる。
つねに一人ひとりが感染対策に対する意識をもつことができるようになるためには、一定のトレーニングが必要である。
たとえば体位呼吸療法を行う場合は、シミュレーションなどで事前に職員の曝露と病院感染を含むリスクの発生を予測し、医師や理学療法士など多職種間で意見交換を行う機会をもつことが有効であると考える。
ウィズコロナではココに注意!
チームで取り組む人工呼吸管理
ウィズコロナにより、感染対策を必要とする場面が増えたことで、適切なタイミングでの手指衛生やPPEの着脱が行えなくなっていることが現場で確認されることがある。さらに、基本的なケアについても、過剰な感染対策を行うなかで省略されてしまうことも懸念される。人工呼吸管理において、患者のケアはすべて医療従事者の手にゆだねられる。患者と医療従事者双方の感染を予防するためのベッドサイドのケアについて、人工呼吸管理の現場の現状と照らし合わせながら振り返ってほしい。
また、人工呼吸器を装着した患者はケア度も高く、さまざまな角度からアセスメントやアプローチが必要となるため、一人で抱え込まず、チームで取り組むことができるような組織作りが大切である。つねにみんなでCOVID-19の感染リスクを踏まえた情報の共有と、一定の治療・ケアの方向性の統一をしておくことが、患者の予後に影響すると考える。
【 引用・参考文献 】
| 1. | 日本呼吸療法医学会ほか.新型コロナウイルス肺炎患者に使用する人工呼吸器等の取り扱いについて-医療機器を介した感染を防止する観点から-Ver.3.0. https://www.ja-ces.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/5fbe4ea278dcc2c72431fc28f502af61.pdf |
| 2. | 日本クリティカルケア看護学会ほか.COVID-19重症患者看護実践ガイドVer.3.0. https://www.jsicm.org/news/upload/COVID-19_nursing_guide_v3.pdf |
| 3. | 日本環境感染学会.医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第4版. http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide4.pdf |
| 4. | Klompas, M. et al. Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia, ventilator-associated events, and nonventilator hospital-acquired pneumonia in acute-care hospitals :2022 Update. Infect Control Hosp Epidemiol.43 (6), 2022, 687-713. |
| 5. | 高田徹.韓国からの持ち込み例を端緒とした多剤耐性 Acinetobacter baumanniiによるアウトブレイク事例. IASR.31. 2010, 197-8. |
| 6. | 日本集中治療医学会.人工呼吸関連肺炎予防バンドル2010改訂版. https://www.jsicm.org/pdf/2010VAP.pdf |
| 7. | Álvarez-Lerma, F. et al . Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia: The Multimodal Approach of the Spanish ICU “Pneumonia Zero” Program. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5770104/pdf/ccm-46-181.pdf |
| 8. | 刑部敦ほか.わが国におけるクロルヘキシジングルコン酸塩によるアナフィラキシー発生についての文献的考察. 日本環境感染学会誌.30(2),2015, 127-34. |
| 9. | 日本クリティカルケア看護学会.気管挿管患者の口腔ケア実践ガイド. https://jaccn.jp/assets/file/guide/OralCareGuide_202102.pdf |
提供元:INFECTION CONTROL 2023 vol.32 no.3
(メディカ出版)
関連商品
関連商品はありません。
関連記事
新着一覧

第7回気道管理学会学術集会 スポンサードセミナー1「Anesthesiologists be ambidextrous!!~両手利きこそが気道管理マスターの条件~」
セミナー情報
日本睡眠学会第48回定期学術集会 ランチョンセミナー3「閉塞性睡眠時無呼吸の個別化治療に踏み出す前にすべきこと ~CPAPの個別化治療を探る~」
特別企画
令和6年度診療報酬改定の概要について③
特別企画
NPPVとハイフローセラピーの比較 こんなときはどちらを選ぶ?
抜管後、再挿管リスクを1つ以上有するケース
特別企画 
令和6年度診療報酬改定の概要について②
特別企画
人工呼吸管理時の感染対策チェックリスト ―実践編―
イベントスケジュール
保守点検技術講習会スケジュール
現在開催の予定はございません
展示会・セミナースケジュール
第46回日本呼吸療法医学会学術集会
2024年6月28日 ~ 6月29日
美味求真の宿 天童ホテル/緑の迎賓館 アンジェリーナ/天童市市民プラザ
第7回気道管理学会学術集会
2024年7月6日
札幌医科大学 教育講義棟
第32回日本乳癌学会学術総会
2024年7月11日 ~ 7月13日
仙台国際センター
第27回日本臨床救急医学会総会・学術集会
2024年7月18日 ~ 7月20日
かごしま県民交流センター
日本睡眠学会第48回定期学術集会
2024年7月18日 ~ 7月19日
パシフィコ横浜ノース